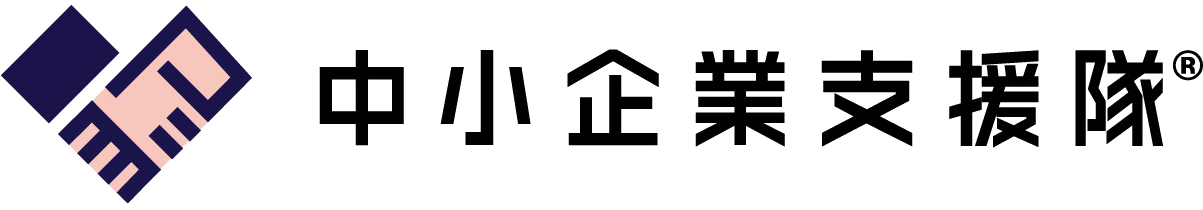こんにちは!
助成金申請サポートの中小企業支援隊です。
毎年7月の末頃に発表されている
「雇用均等基本調査」をご存知ですか?
この調査で令和元年から年々上昇傾向にあり、
昨年の調査結果で大幅に上昇したものがあります。
ーーーーーーーーーーーー
令和5年:30.1%
令和4年:17.13%
令和3年:13.97%
令和2年:12.65%
令和元年:7.48%
それ以前は6%以下
ーーーーーーーーーーーー
この数字なんだと思いますか?
これは、「男性の育休取得率」なんです。
大企業では「あたりまえ」になってきたことで
「男性の育休取得率」が大幅上昇に繋がったようです。
大企業に浸透してきたということはどうなるか?
そうです。
直近の法改正により「中小企業での取得を促進すること」が明確になりました。
国は企業規模に関わらず
「男女ともに働き・男女ともに子育てすること」を目指し
推進しているということです。
とはいえ、常に少数精鋭で頑張っている私たち中小企業にとっては、
「人員が1人でも減ると仕事が回らなくなる」
「育休を取られると他の従業員の負担が大幅に増える」
「代替要員が準備できない」
といった悩みも出てきます。
もし男性社員から
「秋頃に子供が生まれます」と報告されたら、
どうしますか?
「なんと答えるのが正解か」を管理職の社員に周知されていますか?
準備は万全ですか?
「令和7年10月1日から義務化」される内容を知っておかないと
大問題が起こるかもしれません。
そこで、今回のご案内は
「男性の育休取得の正しい知識」と「知っておきたい国の制度」の活用
についてお伝えします。
【本日の内容】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.「知らなかった」が大問題となる義務化の内容
2.育休取得中の給与はどうなる?
3.助成金で最大120万円支給(中小企業限定)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
《1.「知らなかった」が大問題となる義務化の内容》
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和4年に「育児・介護休業法」が改正されて以降、
年々法整備が進んでいます。
令和7年4月1日から段階的に施行されていますが、
今回は10月1日から義務化される重要な項目を確認しておきます。
【令和7年10月1日から義務化】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
妊娠・出産の申し出をした労働者に対して、
育休・産後パパ育休制度の周知ならびに
意向確認を行うことを義務化する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
となっています。
つまり、冒頭にあったように、「秋頃に子供が生まれます」と報告を受けた場合
上司は「そうか!おめでとう!!仕事との両立がんばれ!」
という回答はNGとなります。
部下から「育休取得」を切り出されなくても、
出産の報告を受けた場合は
ーーーーーーーーーーーーーーーー
・育休の制度があることを伝える
・取得するかの意思確認
ーーーーーーーーーーーーーーーー
を必ず行わなければいけません。
もし、「子供が生まれるので育休を取りたいです!」
と言われた場合に、
「育休はちょっと・・・」
「うちの会社にはそんな制度はない」
「男が育休を取るなんてありえない。俺の時代は育休なんてなかった」
「育休を取ったら、いまのポジションでは働けないよ」
などと答えてしまうと大問題にも発展しかねません。
当然ですが
「育休あるけど取るわけないよね?」
と圧力をかける行為もNGです。
また、有期契約社員などの非正規社員も同様に「育休取得」の対象です。
(※ただし、雇用時期などによる条件あり)
知らずに
「正社員じゃないのに育休なんてないよ」
と答えてしまい、
労基署に相談されてしまうと指導や是正勧告を受ける可能性があります。
部下がいる社員や管理職の社員は
「会社のルールではなく、法律による義務であること」を
必ず知っておかなければいけませんので、周知徹底が重要になります。
【10月1日以降の義務内容】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
会社規模に関わらず全ての労働者において
個別の意向の聴取および配慮することが
事業主に義務付けられます。
育休取得によって
減給や復帰後の部署移動など
不当に扱うことも禁止されています。
労働者から育児休業の申し出があった場合、
会社は原則としてその申し出を拒むことはできません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2.育休取得中の給与はどうなる?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
育休中の給与は原則「支払いの義務はありません」
「育児休業」は休暇ではなく休業です。
有給休暇などとは異なるため、労働していない間の賃金は発生しません。
では、育休を取得する労働者は収入がなくなるか?
というとそうではありません。
雇用保険から支給される『育児休業給付金』が受け取れます。
しかも今年から手取り100%相当が給付されるようになりました。
まず「育児休業給付金」を活用することで、休業開始時の賃金の67%が給付。
さらに今年2025年の4月からは育休取得中の収入減の不安を解消するために
「出生後休業支援給付金」が新しく創設されました。
これにより、休業開始時の賃金の13%分が加算されます。
育児休業給付金:67%
出生後休業支援給付金:13%
合計 80%が支給されます。
この給付金はどちらも、健康保険料・厚生年金保険料が「免除」され、
育児休業給付金は「非課税」のため、
給付率80%でも直前の手取り100% 相当の給付金額となります。
※支給される期間や支給額には上限がありますので、
勤続年数や出産日などを正確に把握する必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3.助成金で最大120万円支給(中小企業限定)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
男性の育休取得が義務になるなら、
取得できる環境を整えることで、助成金を貰えた方が良いと思いませんか?
社員の育休取得時には
「両立支援等助成金」の「育児休業支援コース」が活用いただけます。
※ただし「中小企業」限定になります。
助成金額は
・育休取得時 に30万円
・職場復帰時 に30万円
・育休情報公表時に2万円(1回限り)
無期雇用労働者・有期雇用労働者それぞれ1人ずつ申請可能
となります。
「育休取得時」「職場復帰時」それぞれに、
労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組むための要件がいくつかあり、
育休復帰支援プランを作成し、そのプランに基づき育休を取得させる必要があります。
また、復帰後は対象労働者を原則として原職等に復帰させ、
申請日までの間6か月以上継続雇用が必要になります。
弊社にご依頼いただいた場合は、
申請のサポートだけではなく、
プラン作成のサポートや就業規則の改定、
各種必要資料の作成なども合わせてサポートいたしますのでご安心ください。
令和7年度申請のサポートのご依頼はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
《「育休取得で使える助成金」お問い合わせフォーム》
https://forms.gle/DfWGsP9u692xSv9d7
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
《まとめ》
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
育休が取得できる会社ということは
「従業員を大切にする会社」
「働きやすい会社」
といったイメージに繋がり、採用活動にもプラスの効果が期待できます。
また、社員が1人休業する環境で仕事を円滑に回すためには
業務の見直しが必要になります。
育休は取得する日が予測できるため、事前に業務効率化を見直す時間が取れたり、
社員のスキルアップやリスク分散を考えるきっかけにもなります。
結果として、生産性の向上にも繋がると考えられます。
育休の取得促進は会社にとってメリットが大きいと思いませんか?
心地よく育休をとってもらい、快く戻ってきてもらいましょう。
その環境こそが、
若手が望む「働きやすく長く続けたい会社」に繋がります。
【参照】厚生労働省:両立支援等助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/001240558.pdf